
【草津・野路町の原風景を歩く】川ノ下と南田山──歴史が息づく信仰と暮らしの地
滋賀県草津市・南草津エリアの発展が進む中で、ひっそりと佇む「野路町 川ノ下(かわのした)」と「南田山(なんだやま)」地域。
新しい住宅や商業施設が増える一方で、これらの地区には、古くからの地形や神社仏閣、そして人々の暮らしに寄り添う信仰が息づいています。
今回は、この二つの地区に焦点を当て、地名の由来や史跡、神社・寺院の歴史をたどりながら、地域の魅力を深掘りします。
地名に刻まれた「川ノ下」の記憶──天井川がつくった集落
「川ノ下」という地名は、草津川や十禅寺川の影響を受けた独特の地形に由来します。
かつて草津川は“天井川”と呼ばれる、川床が周囲の地面より高くなる特異な川でした。その川の“下手”にあたる場所が、「川ノ下」と呼ばれるようになったのです。
この地には、奈良時代からの集落遺跡「野路岡田遺跡」も確認されており、時代を経て、室町期〜江戸初期には矢橋街道沿いに人々が住まいを移していったことが、発掘調査などからも明らかになっています。
江戸初期の信仰を今に伝える「川ノ下猿田彦神社」
川ノ下集落の守り神として、今も地元に大切にされているのが猿田彦神社です。
創建は江戸時代初期・寛永2年(1625年)。矢橋街道沿いに位置し、旅人や商人の道中安全を祈願して建立された神社です。
ご祭神である**猿田彦命(さるたひこのみこと)**は、道案内の神・交通の神として知られ、古来より集落の鎮守として信仰されてきました。現在でも、地域の行事は野路本郷の新宮神社の宮司により執り行われており、地域のつながりが今も生きています。

江戸期の農地開拓とともに誕生した「南田山」集落
川ノ下から南西に広がる南田山地区は、江戸時代に膳所藩の農地開拓政策のもとで開かれた新しい集落です。
もともと田畑や古墳が広がる未開地だったこの場所に、人々は十禅寺川沿いや榊差古墳群周辺を耕し、村を築きました。
その後、地域の精神的支柱となったのが、次の二つの信仰施設です。
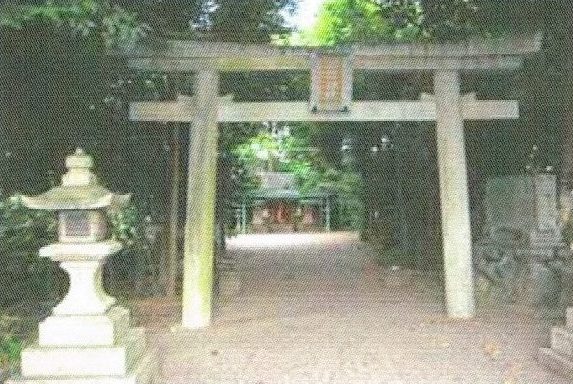
信仰と農の神が宿る「南田山稲荷神社」
南田山の高台に鎮座する南田山稲荷神社は、宝暦3年(1753年)の創建。
ご祭神は、五穀豊穣・家内安全・商売繁盛を司る「宇迦之御魂命(うかのみたまのみこと)」。別名「豊受姫命(とようけひめのみこと)」としても親しまれています。
この神社は、南田山に暮らす人々が、日々の糧と安寧を祈り続けてきた“地の神”ともいえる存在。現在も春秋の祭礼や地域の行事が行われ、住民の信仰が続いています。
野路で一番新しい寺「高岸寺」
南田山に位置する**高岸寺(こうがんじ)**は、宝暦8年(1758年)に浄土宗鎮西派の僧・憲誉部(けんよぶ)によって創建されました。
寺域は250坪ほどとコンパクトながらも、南田山を中心に地域の仏教信仰を支えてきた寺院です。
興味深いのは、川ノ下の住民もこの寺の檀家として名を連ねている点。地理的に離れていても、人々の信仰やつながりはしっかりと継承されてきたことがわかります。

いま再び注目したい“野路の歴史風景”
川ノ下や南田山のように、草津の都市化に取り残されることなく、静かに歴史をとどめる地域は貴重な存在です。
旧道沿いには道標や常夜灯、地蔵堂などが点在し、往時の風情を感じさせてくれます。
歴史とともに暮らし、祈りを絶やさず守り続けてきた人々の姿が、今の地域文化の基盤となっているのです。
おわりに:風景のなかに宿る“信仰”と“地形”の記憶
川ノ下と南田山を歩いてみると、そこには一見目立たないけれど、確かに根付いた土地の記憶が存在します。
信仰を軸に生きた人々の営み、川や街道に沿って変遷してきた集落の歴史、そして今も静かに佇む神社や寺院。
それは「古いけれど新しい」――南草津のもう一つの表情として、これからも語り継がれていく地域の物語です。

草津市 野路町・川ノ下・南田山の基本情報
◆ 地理と地名の由来
「川ノ下(かわのした)」は、滋賀県草津市野路町の南西部に位置する一帯で、草津川(旧天井川)と十禅寺川の合流域近くに広がる地域です。
地名は天井川特有の地形(周囲より高い川床)にちなみ、“川の下手の集落”を意味するとされています。近年では宅地開発や都市化が進みつつも、旧東海道や矢橋街道の名残をとどめる町並みや史跡が点在し、地域のアイデンティティを保っています。
◆ 歴史的背景
野路町は、かつて平安時代の“東山道”の宿駅「野路宿」として発展。源義経や北条時房などの通過が記録に残るなど、交通の要衝でした。
江戸期以降は旧東海道の一里塚、宿場町として栄え、南草津駅開業後の現代にかけては住宅地化が急速に進んでいます。
川ノ下地域では、奈良時代の集落遺跡「野路岡田遺跡」が知られており、ここを拠点とした村落が中世以降に矢橋街道沿いへ移転。これは発掘調査からも裏付けられています。
◆ 主な神社・寺院と文化資産
● 川ノ下 猿田彦神社(寛永2年=1625年創建)
- 江戸時代初期、川ノ下集落が形成された時期に建立された神社で、交通安全・道の神として知られる「猿田彦命(さるたひこのみこと)」を祀ります。
- 神社は北川と矢橋街道の間に位置し、集落の鎮守・道中安全を祈願する拠点。
- 祭礼は野路本郷の新宮神社と共通し、新宮神社の宮司によって執行されています。
● 南田山 高岸寺(宝暦8年=1758年開山)
- 野路町南田山にある浄土宗鎮西派の寺院で、創建は江戸後期。
- 僧 憲誉部(けんよぶ)によって開基され、野路地域ではもっとも新しい寺院です。
- 現在の檀家構成には川ノ下集落も含まれており、歴史的にも地域をまたいだ信仰が根づいています。
● 南田山 稲荷神社(宝暦3年=1753年創建)
- 江戸時代中期に野路榊差(さかきざし)の霊地に創建された、宇迦之御魂命(うかのみたまのみこと)を祀る稲荷神社。
- 豊受姫命(とようけひめのみこと)とも称され、五穀豊穣・家内安全・商売繁盛を司る神様。
- 南田山地域の集落は、膳所藩による農地開拓政策(江戸時代)で開発された十禅寺川沿い・榊差古墳群周辺に形成されたものと考えられています。
◆ 地域文化と自然
- 川ノ下・南田山は、草津市南部にあって古代・中世の地形と信仰を色濃く残すエリアです。
- 「萩の玉川」や「野路一里塚」といった名所も近く、文学・史跡・民俗信仰が融合した文化的背景があります。
- 特に川ノ下には道祖神や地蔵、常夜灯などが点在し、地元住民による保存・維持活動も継続されています。
◆ 現在の地域の様子
| 項目 | 概要 |
| 所在地 | 滋賀県草津市野路町(川ノ下・南田山) |
| 主な宗教施設 | 猿田彦神社、高岸寺、南田山稲荷神社 |
| 交通 | 矢橋街道・旧東海道・国道1号に接近、JR南草津駅から車で5分前後 |
| 地形 | 草津川(旧天井川)・十禅寺川沿いの平坦地/農地と宅地の混在 |
| 開発状況 | 近年の都市化により宅地造成が進行中/一部に歴史的景観保持 |
| 文化性 | 野路岡田遺跡、地蔵堂、旧道沿いの石標や民間信仰の継承など |
◆ 総括:地域に息づく“信仰”と“地形”の記憶
川ノ下や南田山地区は、草津市の発展とともに変化を続けながらも、地形的な特徴や古来からの信仰を今に伝える貴重な地域です。江戸期から続く神社や寺院は、集落の成立や街道交通の記憶と密接に結びついており、現代においても地域の心の拠り所となっています。
